小学生の「防犯」と「連絡手段」どうしてる?
小学生になると、子どもが一人で出かける機会がグッと増えます。
習い事への行き帰りや、友達と遊びに行くときなど、「無事に着いたかな?」「今どこ?」と不安になることも。
そんなときに便利なのが、GPS付きの連絡手段です。
私も、小1の息子が習い事を始めたのをきっかけに「位置がわかって、必要なときに連絡が取れるアイテムが欲しい」と思うようになりました。
でも「スマホ」はちょっと早いかも…?
最近は子ども向けスマホ(キッズスマホ)も増えていますが、
- アプリを勝手にダウンロードされそう
- ゲームやYouTubeの見すぎが心配
- SNSやネットのトラブルも怖い
…と、まだちょっと心配ですよね。
私も「スマホはまだ早いかな」と思っています。
まずは“使い方を練習する期間”に!
いずれスマホを持たせるにしても、
- GPSや通話、防犯ブザーなど必要最低限の機能のみ
- 家族との連絡に慣れる
- 夜は電源を切るなどのスマホに近いルールを取り入れる
というステップを踏めば、自然とスマホ移行の準備ができます。
そのためにおすすめなのが、**「キッズ携帯」**です!
小学生低学年にはキッズ携帯、中高学年からはHamicも!
小学校低学年のうちは、親と同じキャリアで契約できるキッズ携帯がシンプルでおすすめ。
- 各キャリア(ドコモ・au・ソフトバンク)の安心サポート
- 通信・通話制限がしっかり
- 本体代や月額料金もリーズナブル
一方で、小学生高学年〜中学生にかけては、スマホに慣れる練習としてHamic(ハミック)シリーズもぴったり!
- メッセージアプリでやり取りの練習
- カメラ付きで日常記録も楽しめる
- 必要な機能に絞られた設計で依存を防ぐ
子どもの成長に合わせてステップアップしていくのが理想的です。
キッズ携帯 vs キッズスマホ 何が違う?
| 比較項目 | キッズスマホ | キッズ携帯 |
|---|---|---|
| 機能 | スマホとほぼ同じ | 通話・GPSなど最低限 |
| 制限 | 保護者の制限が必要 | 最初から制限された仕様 |
| 遊び | ゲーム・動画あり | なし or ごく少量 |
| メリット | 長く使える・便利 | 安全性が高く依存リスク低 |
| デメリット | 管理が手間・依存リスク | 機能がシンプルすぎる場合も |
【2025年版】小学生におすすめのキッズ携帯まとめ
キッズ携帯選びのポイントは以下の通り:
- 初期費用(本体価格)と月額料金など
- 通話・通信機能
- GPSや防犯ブザーの有無
- メッセージ機能(LINE風など)
- バッテリーの持ち
- カメラの性能
| 項目 | ドコモ(KY-41C) | au(mamorino6) | ソフトバンク(キッズフォン3) | Hamic nico |
|---|---|---|---|---|
| 初期費用 | 約22,000円 | 約22,000円 | 約20,880円 | 29,700円(レンタル3,300円) |
| 月額料金 | 550円~ | 660円~ | 539円~ | 1,100円~(2,200円~) |
| 通話機能 | 〇(ドコモ同士の家族無料) | 〇(家族間無料) | 〇(5分以内無料、ソフトバンク同士の家族は無制限) | 〇 |
| SMS | 〇(無制限) | 〇(家族間無料) | 〇(ソフトバンク同士無料) | なし |
| GPS | ○(+220円) | ○(+330円) | ○(+220円) | ○(無料) |
| 防犯ブザー | ○(約100dB) | ○ | ○ | ○ |
| メッセージ機能 | 〇(+メッセージで写真も送れる) | 〇(+メッセージで写真も送れる) | 〇(+メッセージで写真も送れる) | 〇(専用アプリなのでHamic内のみ) |
| バッテリー | 1500mAh | 1540mAh | 1700mAh | 3500mAh |
| カメラ | 約500万画素(メイン・サブ) | 約500万画素(メイン)
約200万画素(サブ) |
約800万画素(メイン)
約500万画素(サブ)
|
1,300万画素(メイン)
800万画素(サブ) |
| その他 | 防水・防塵 | 防水・防塵 | 防水・防塵 | 防水・防塵・ 電源切れでも位置情報ON・インターネットも使用可能 |
小学生低学年の時は、キャリアのキッズ携帯、中高年にはHamicがぴったりそう!
まとめ:スマホ前の「練習アイテム」にぴったり!
キッズ携帯は、スマホの前段階としてちょうどいい存在。
- GPS、防犯ブザー、通話など基本機能あり
- ゲーム・SNSなしで安心
- 家庭で「スマホルール」を練習できる
小学生低学年のうちは、親と同じキャリアのキッズ携帯が安心。
そして高学年〜中学生になったら、Hamicのようなスマホに近い端末で、 「使い方のルール」や「マナー」を徐々に身につけていくのがおすすめです。
子どもも親も安心できる第一歩として、ぜひライフスタイルに合った1台を選んでみてくださいね。


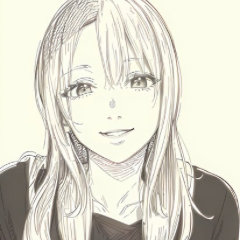
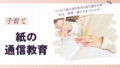
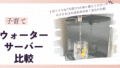
コメント