幼児の習い事、何歳から始めた?
我が家では、息子が0歳半のときから習い事をスタートしました。きっかけは、「親がまず学ぶ必要がある」と感じたからです。幼児期は、子どもにとって人生で最も吸収力が高い時期。だからこそ、まずは親が正しい接し方や環境の整え方を学び、しっかりと土台をつくってあげたいと思いました。
幼児期にやってよかった習い事|年齢・内容・効果
①ベビーパーク(0歳半〜3歳)

最初に通ったのが、親子教室のベビーパークです。幼児期は親の影響をダイレクトに受ける大切な時期。だからこそ、親が子どもへの接し方を学べる場が必要だと感じて選びました。
月謝は決して安くはなかったですが、それ以上の価値がありました。優しく、思慮深く、精神年齢の高い息子に育ったのは、ベビーパークで学んだ親の接し方を私が意識して実践してきたからだと思っています。今でもあの頃の学びが私自身の子育ての軸になっています。心からおすすめしたい教室です。
②キッズアカデミー(3歳〜小1現在も継続中)

ベビーパーク卒業後、そのまま進級して通い続けているのがキッズアカデミーです。
小学校の学びをスムーズに受け入れるために、概念理解を「遊びを通して」身につけられるカリキュラムになっており、机に向かって集中する力や思考力も自然と育っていきました。
幼児教室はキッズアカデミーでなくてもいいと思いますが、「小学校までに何らかの形で概念の土台を作る」ことはとても大切だと実感しています。
③こどもちゃれんじ(1歳〜年少)

年齢にぴったり合ったおもちゃや絵本が届くこどもちゃれんじ。0歳〜3歳頃の吸収力が高い時期には本当におすすめです。
特に絵本は優秀で、息子が絵本好きになったのはしまじろうのおかげだと思っています。年中以降、勉強色が強くなったことで解約しましたが、それまではコスパも内容も大満足。
他にもおもちゃのサブスクや絵本の定期便も試しましたが、我が家では「しまじろうだけで十分」と感じました。
④体操(年少〜年長)

私は運動が苦手で運動神経にも自信がなかったため、息子には早いうちから運動に触れさせたいと思っていました。
結果として、前回りや逆上がり、跳び箱などを幼児期に身につけることができ、本人の自信にもつながったと思います。身体を動かすことの楽しさを知ってくれたのは大きな収穫でした。
⑤将棋(年少〜現在も継続中)

将棋は異年齢の子どもたちと関われる貴重な習い事でした。年少〜年長の頃は、年上の子の姿を見て学ぶことができ、現在は大人もいる教室に通っています。
小学生・中高生・大人と関われる環境は、息子にとってとても良い刺激になっています。集中力や論理的思考力が自然と育つのも将棋の良さだと感じています。
やらなくて後悔した習い事
ビーマスポーツ(小1〜)
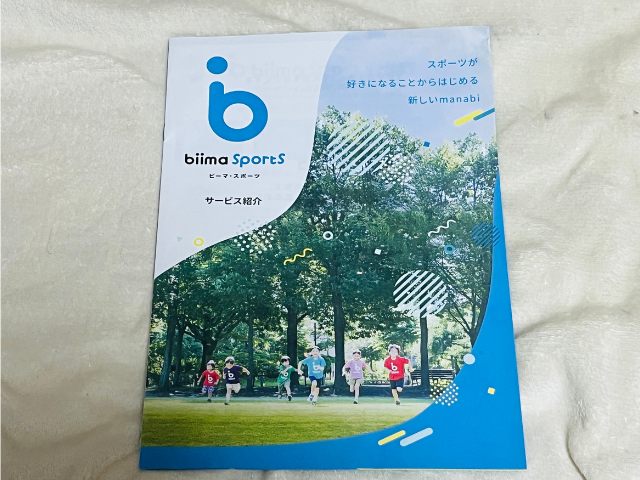
ビーマスポーツはさまざまなスポーツを2ヶ月ごとに体験できる教室で、運動神経をまんべんなく育てられる内容です。
現在小1から通い始めましたが、「もっと早く始めておけばよかった…!」と後悔。幼児期の方が体の動きに対する柔軟性があり、より多くの可能性を広げられたと感じています。
時期尚早だった習い事
①ワンダーボックス(年長)
ワンダーボックス ![]() は年長の1年間継続しました。内容自体はとても良く、STEAM分野を自宅のタブレットで楽しく学べます。ただ、幼児期にタブレット漬けになることが気がかりで、次第にやらなくなり退会。
は年長の1年間継続しました。内容自体はとても良く、STEAM分野を自宅のタブレットで楽しく学べます。ただ、幼児期にタブレット漬けになることが気がかりで、次第にやらなくなり退会。
STEAM教材としては本当に良質なので、小学生になってから興味を持ったタイミングで始める方が合っていたかも、と感じました。
②プログラミング教室
レゴなどのプログラミング系は面白そうでしたが、幼児期のうちは「好きかどうか」もまだ分からない状態。
ScratchJrなど無料ソフトで軽く触れる程度で十分。幼児期は無理に詰め込まず、興味を持ってからで間に合うと感じました。
幼児期の習い事で大切だと思うこと
①幼児期は「親が学ぶ時期」
子どもは親の行動を見て育ちます。子どもに勉強してほしければ親が勉強している姿を、読書してほしければ親が本を読んでいる姿を見せる。習い事以上に、「日常の中の親の在り方」が子どもに影響すると考えています。
②幼児期に勉強は不要、とにかく遊べ!
遊びの中でこそ、子どもは学びます。良質なおもちゃや教材で思い切り遊ばせることが、最も効果的な知育になると実感しています。
しまじろう教材やキッズアカデミーのように「遊び×学び」の教材をうまく取り入れるのがポイントです。
③良質な運動経験が差を生む
私自身が運動嫌いだったからこそ、幼児期に体をたくさん動かすことを意識しました。運動神経はある程度「慣れ」が必要。だからこそ、小さいうちにどれだけ体を動かすかが大切だと感じています。
④タブレット教材は慎重に
便利で楽ですが、依存性や視力低下のリスクも。タブレット教材はどうしても「勉強要素」が強くなりがちなので、我が家ではあえて避けました。どうしても使いたいなら、無料のプログラミング教材(例:ScratchJrなど)で十分だと考えています。
⑤英語は焦らなくてOK
我が家では英語に力を入れていません。実際に英語が堪能な友人たちは、幼児期に英語教育をしていたわけではなく、必要に迫られて留学やワーホリで身につけたパターンが多いです。
まずは母国語をしっかり育てることが大切。その上で、外国人とのふれあいや異文化体験の方がよほど価値があると感じています。
⑥「長く続けられる習い事」を1つ持とう
学校や家庭以外に「安心できる居場所」があると、子どもはぐっと安定します。
我が家にとってはそれが将棋教室。大人になっても続けられる習い事があることで、自信や自己肯定感にもつながっています。
まとめ
習い事は、子どもだけでなく親にとっても学びの連続です。無理に増やす必要はありませんが、子どもの興味・成長段階・家庭のペースに合った習い事を取り入れていくことが、豊かな幼児期につながると感じています。
そして何より大切なのは「親がどう子どもと向き合うか」。習い事を通じて、それに気づけたことが我が家にとって一番の収穫でした。
一番向き合える時間の長い幼児期に、より時間をかけて接してあげてください。
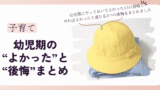
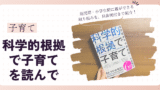


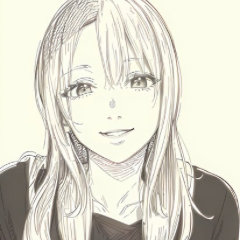
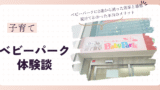
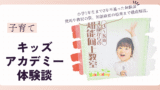



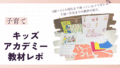
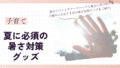
コメント